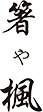よりそい箸「流水と桜・紅葉」について
よりそい箸とは
「よりそい箸」は、箸や楓が考案した、二膳でひとつの絵柄を描く新感覚の夫婦箸です。
左右の箸が寄り添い、一対となって一幅の絵を完成させるその姿は、ふたりの絆を象徴しています。
箸や楓が提案する「ハレ箸」は、
「衣服に晴れ着があるように、お箸にも特別な日のための一本を」という想いから生まれました。
お正月や節句、結婚記念日、誕生日など、人生の節目に使う「晴れの日の箸」です。
大切な記念日にこの箸を使えば、年月とともに思い出が深まり、一生の宝物になるでしょう。
毎日使うものではないからこそ、長く寄り添い続けられる――
そんな願いを込めた「よりそい箸」は、結婚祝いや記念日の贈り物に最適な一品です。
流水と桜・紅葉柄について
「流水に桜が浮かぶ文様」は、古くから日本で愛されてきた伝統意匠のひとつで、「桜川」とも呼ばれます。
この文様には、「始まりが絶えず続くこと」「おめでたい出来事が連なること」という吉祥の意味が込められています。
流れる水は清らかさや再生を象徴し、苦難や災厄を流し去るという祈りの心を表しています。
その意匠は、古代の土器や銅鐸にも見られるほど、長い歴史と信仰に支えられてきました。
桜は「豊かさ」や「新たな門出」の象徴。
咲き誇る花々の姿は「良きことの始まり」を表し、春の訪れとともに明るい未来を感じさせます。
また、流水に紅葉を組み合わせた文様は、秋の情緒を映す優美な意匠として親しまれています。
紅葉には「長寿」や「世渡り上手」の意味があり、流れゆく水とともに季節のうつろいを美しく表現しています。
これらの文様は、日常の器や贈答品などにも幅広く用いられ、
私たちの暮らしに彩りと意味を添えてきました。
伝統の意匠を通じて、季節の移ろいや自然の美しさを感じ取る――
それこそが、日本の美意識の一つです。
よりそい箸「流水と桜・紅葉」
「よりそい箸」に、自然の情景を描いた「流水と桜・紅葉」のデザインを施しました。
黒漆の落ち着いた地に流れる水の動きを描き、その両側に春の桜と秋の紅葉を配しています。
ふたつの季節がひとつの世界で寄り添うように、対の箸が調和する美しいデザインです。
この意匠は、「雲錦(うんきん)」という日本の美意識から着想を得ています。
雲錦とは、満開の桜を白雲に、紅葉を錦織に見立てた言葉で、自然の移ろいを詩情豊かに表現したものです。
流れる水とともに桜と紅葉を描くことで、春と秋が出会い、
時の儚さと永遠を同時に感じさせるお箸に仕上げました。
「流水と桜・紅葉」は、春や秋を象徴する図案でありながら、
落ち着いた華やかさを持ち、四季を通してお使いいただけます。
特に和食の席では、料理の彩りと調和し、食卓に上質な風情を添えてくれるでしょう。





日本文化の粋を贈り物に
このお箸は、日常の食卓に優雅さを添えるだけでなく、
結婚祝いや長寿祝い、季節の節目の贈り物、さらに海外へのギフトにも最適です。
日本文化の美と心を込めた「よりそい箸『流水と桜・紅葉』」。
手に取るたびに、四季の移ろいとともに、心豊かな時間を感じていただけることでしょう。
関連情報
晴れの日のハレ箸 - 箸や楓 (hasiyakaede)
「衣服に晴れ着があるように、お箸にも晴れの日に使う晴れ箸」があってもと考えています。日本には、お正月にはじまりクリスマス、その他にも誕生日、結婚記念日など、それぞれの晴れの日が考えられます。箸や楓の思いは、普段着と晴れ着があるように、箸にも普段使いの箸とそんな晴れの日に使う「ハレ箸」があってもよいのではということです。
| 屋号 | 箸や楓 |
|---|---|
| 住所 |
〒605-0826 京都府京都市東山区桝屋町362番地12 |
| 営業時間 | 11:00~17:00 |
| 定休日 | 木曜日 |
| 代表者名 | 橋本 良介 |
| info@hasiyakaede.com |