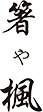漆器の装飾技法のひとつ「螺鈿」
螺鈿細工とは
螺鈿は、奈良時代に唐から伝来した伝統技法で、漆器やその他の工芸品の表面におうむ貝やあわび貝などの真珠色の光を放つ部分を切り取り、はめ込んで装飾する技法です。この技法は、数ある工芸品の中でも特に美しいとされる伝統的な加飾技法のひとつです。高岡では、主にアワビ貝を使い、0.1mmまで薄く削った薄貝を針で切り抜いて使用します。螺鈿では幾何学模様や伝統的な花鳥風月の柄だけでなく、文字やロゴ、キャラクターなど様々な形状や色を表現できるのが特徴です。漆器などに施されるこの装飾は、まるで宝石のような美しさを持ちます。螺鈿の技法は、材料となる貝に彫刻を施し、漆器の表面や木地にはめ込むことで完成します。この技法は非常に繊細で、わずかな加減で表面の輝き方や色合いが異なるため、それぞれの作品が唯一無二の魅力を持ちます。使用する貝の種類によっても仕上がりが異なるため、様々な文様や模様を表現できるのが螺鈿の魅力のひとつです。
螺鈿技法を駆使した漆器は、伝統美と現代のデザインが融合した作品として、多くの人々に愛されています。
螺鈿千筋箸
螺鈿千筋箸は、螺鈿と呼ばれる貝殻の装飾が細かなライン状に施された箸です。繊細なデザインは和風・洋風を問わず、どんな食卓にも調和します。この美しい箸を使うことで、食事の時間が一層特別なものになり、落ち着いたやわらかな雰囲気を楽しむことができます。職人の手による精緻な技術が光る一品です。デザインの細やかさと光沢が、食卓に華やかさと品格を添えてくれます。




関連情報
晴れの日のハレ箸 - 箸や楓 (hasiyakaede)
「衣服に晴れ着があるように、お箸にも晴れの日に使う晴れ箸」があってもと考えています。日本には、お正月にはじまりクリスマス、その他にも誕生日、結婚記念日など、それぞれの晴れの日が考えられます。箸や楓の思いは、普段着と晴れ着があるように、箸にも普段使いの箸とそんな晴れの日に使う「ハレ箸」があってもよいのではということです。
| 屋号 | 箸や楓 |
|---|---|
| 住所 |
〒605-0826 京都府京都市東山区桝屋町362番地12 |
| 営業時間 | 11:00~17:00 |
| 定休日 | 木曜日 |
| 代表者名 | 橋本 良介 |
| info@hasiyakaede.com |